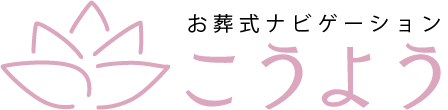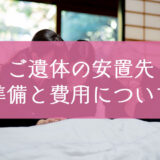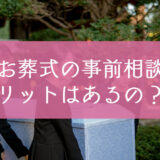訃報は受けるのも出すのも急なもの。いざという時に誰に訃報を出せば良いのか焦ってしまうのが普通です。
ですが、お通夜やお葬式までには準備することはたくさんあるのに、時間は限られているのが現実。少しでも負担を減らすためにも、訃報の出し方と誰に出すべきかをしっかりと決めておくようにしたいですよね。
今回は「お葬式の連絡(訃報)」について詳しくご紹介していきます!
訃報とは
「訃報=お葬式の案内」と思っている方も多いと思いますが、厳密には異なり、訃報にはお葬式などの案内は含まれず、故人様が亡くなったという知らせだけのことを指します。
とはいえ、通信手段の発展した現代では、お葬式の手配が済んでからの連絡でも十分に間に合うため、お葬式の案内を訃報の代わりにすることも珍しくありません。
訃報で伝えるべき内容
訃報は「故人様が亡くなったこと」をお知らせするものですので、基本的には誰が亡くなったのかを伝える事を優先します。
ただし、前述している通り、近年では訃報とお葬式の案内を合わせるのが一般的になっています。
- 故人様の名前・享年
- お通夜、お葬式の日程・場所
- 喪主の名前・連絡先
- 宗教・宗派
- 死因(任意)
死因についてはあまり周りに知らせたくないこともありますので、必ずしも記す必要はありません。病気などで闘病生活が長かった時など、訃報と共に感謝を伝える場合などに記す場合があります。
訃報を伝える相手と順番
訃報を伝える相手(範囲)については、喪主様の自由ではありますが、お葬式の案内の役割を持たせるのが一般的。そのため、基本的には「お葬式に来てほしい人」に限って訃報を出すようにしましょう。
また、順番については故人様(もしくは喪主様)との間柄が近い順に出します。(お葬式の手配に必要な訃報も優先する)
- 家族・親族
- 葬儀社・宗教関係者
- 故人様の関係者
- ご遺族の関係者
- 町内・近所の方
最も優先すべきは故人様のご家族、親族の方。
その次に優先するのは、菩提寺などの故人様の信仰する宗教関係者の方や、葬儀社への連絡です。お通夜やお葬式までには多少日程があるとしても、枕経を含め、必要な場合などお坊さんの手配が必要になるためです。
町内・ご近所の方への訃報は最近ではあまりすることはありませんが、家族ぐるみでお付き合いのあった場合など、お葬式に参列してもらいたい場合は訃報を出すようにしましょう。
訃報を伝える方法
訃報の方法は時代と共に変化しつつあり、必ずしもここで紹介している方法をとる必要はありません。伝えたい人に確実に伝わる方法をとるようにしましょう。
ここでは一般的な方法をいくつかご紹介します。
電話
電話での訃報は最も一般的なもので、とにかく早く伝えるべき相手に伝えるのに適した方法です。ご家族やご遺族など、限られた人数で早急に伝えるべき相手には電話で伝えるようにしましょう。
FAX
一般家庭ではFAXを設置していることはほとんどなくなってしまいましたが、会社関係や耳の不自由な方への訃報などでは有効な方法となります。
手紙よりも確実に早く届けることができるため、電話と同様に早急に伝えたい場合や、言葉で伝えるのが難しい場合などに活用することができます。
メール
メールでの訃報は簡易的なもので、マナー違反と感じられる方もいらっしゃいますが、FAXと同様に手紙よりも早く届けることができるので、関係性によってはメールでの訃報も検討する必要があります。
ただし、近年ではメールの開封率が低くなっている(メールをチェックしない人が多い)こともあり、普段から仕事でメールのやり取りをしている相手などを除いて、メールでの訃報は確実に届ける方法としてはあまり適していません。
LINE・SNS
メールよりも確実な連絡手段として、「LINE」や「SNS」での連絡方法があります。
特にLINEの場合はメールと異なり相手が読んだかどうかがわかるので、確実性も高く、スマホ利用者のほとんどが利用しているアプリのため、ほとんどの方に対して利用できる連絡手段です。
また、SNSのDMや投稿を使って、一斉にお知らせをする場合もあります。お葬式が終わった後の訃報として、故人様のアカウントを使ってご遺族の方が挨拶をすることも増えてきていますね。
案内状(挨拶状)
お通夜、お葬式の案内状として訃報を出す方法です。ハガキとして出すのが一般的ですが、手配に時間とお金がかかること、相手に伝わるまでに時間がかかることを考慮する必要があります。
最近では案内状を数枚用意し、その写真をLINEやSNSで送るといった方法をとることもあります。
現代っぽさのある方法ですが、この方法であればあれば打ち間違いなどによる日程の間違いなどを防ぎつつ、素早く訃報を出すことができます。
訃報を送るタイミングは3つ
訃報は送る相手(訃報を送る意味)によってタイミングが異なり、主に3つの送るタイミングが考えられます。
- 故人様が亡くなった直後
- お通夜・お葬式の日程が決まった後
- お葬式(四十九日)が終わった後
故人様、喪主様のご家族や親しい間柄の人には①故人様が亡くなった直後の連絡、そのほかお通夜・お葬式に参列してほしい方には②お通夜・お葬式の日程が決まった後に訃報を出します。
お通夜やお葬式の予算の都合や、関係性によってはお葬式などの一通りの供養が終わってからお知らせしたい場合もありますので、そういった方への訃報は③お葬式(四十九日)が終わった後に出しても問題ありません。
特に最近では家族葬など、ご家族だけでの供養を望まれるケースも多いので、訃報を出すタイミングも合わせて変えていくようにしましょう。
お葬式の連絡に関するよくあるご質問
- 訃報はメールやLINEで出してもいいの?
- メールやLINEでの訃報は簡易的な方法として、マナー違反と感じられる方もいらっしゃいますが、電話よりもLINEの方が連絡を確実に取れる方も多い時代です。あまり形式にとらわれすぎず、メールやLINEだとしても確実に届けられる方法を選ぶようにしましょう。
- 訃報では何を伝えたらいいの?
- 基本的には「故人様のお名前・享年」「喪主様の名前・連絡先」「お通夜・お葬式の日程・場所」「宗教・宗派」を伝えます。死因については必ずしも伝える必要はありませんが、間柄や死因次第ではお伝えすることもあります。
- 訃報はいつまでに出せばいい?
- 訃報を出す相手によっても異なります。ご遺族や親しい間柄の人など、お通夜・お葬式に参列してほしい人の場合は、故人様が亡くなった直後やお通夜等の日程が決まったらすぐに訃報を出しましょう。
まとめ
今回の記事では「お葬式の連絡(訃報)」について解説してきましたがいかがだったでしょうか?
訃報に限らずお通夜やお葬式に関するマナーは、時代の変化とともに大きく変わってきています。特に通信手段においては昔ながらの方法だと逆に伝わりにくくなることもしばしば。
関係性などによって配慮する必要はあるものの、あまり形式にとらわれすぎず、確実に相手に届く方法で訃報を出すようにしたいですね。また、お通夜やお葬式に参列してもらいたい方には、出来るだけ早く訃報が届くような配慮も必要です。