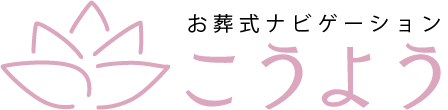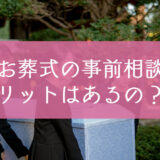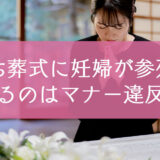日本では礼儀を重んじる風習・文化があり、冠婚葬祭の時には特にそういった風習が目立つもの。身内に不幸があったことをお知らせする「訃報」でも礼儀を大切にする考えが強くあります。
ですが、最近では通信手段の発展や生活習慣の変化もあり、必ずしも礼儀を重要視するのではなく、時には便利さや速さを重要視することもあります。
今回の記事では、素早く多くの人に訃報を伝えることができる「メールでの訃報の出し方」について詳しく解説をしていきます。
メールでの訃報も一般的になりつつある
訃報をメールで送ること自体はマナー違反ではありませんが、あくまでも簡易的なものとして捉えられてきていました。
ですが、最近ではメールだけではなく「LINE」や「SNS」を使って、効率的に素早く訃報を伝えることも増えてきています。
本来は電話や直接会って訃報を伝えることが望ましいとしても、お葬式の準備や精神的な負担を考えると、ご遺族の方が普段から使っている連絡手段を使って、訃報を知らせることも許容した方がいいのかもしれませんね。
メールで訃報を送る時の注意点
メールでの訃報が一般的になりつつあるといっても、普段、友達にメールやLINEを送るような気軽な内容で送ることは避けたいところ。
訃報は普段あまり直接的に連絡を取らない方へも、連絡をすることになりますので、間柄によっては特に慎重になる必要があるかもしれません。
ここではメールで訃報を送る時の注意点について解説していきます。
メールは確実な連絡手段ではない
電話や直接会って訃報を伝える場合、その場で相手からの反応を見ることができますので、相手に伝わっているかどうかを確認することができます。
ですが、メールの場合は相手からの返信がない限り、相手にしっかりと伝わっているかがわかりません。
メールアドレスが間違えている、ビジネスと兼用していてメールが埋もれてしまっている、普段からあまりメールを開かない、迷惑メールに自動で振り分けられてしまっている・・・。
など、メールが開封されない可能性も大いにあるという点に注意をしておきましょう。
件名はわかりやすく簡潔に
メールが埋もれてしまわないようにするためには、メールの件名を出来るだけわかりやすく簡潔にしておくことが重要です。
例えば「お忙しい所の連絡失礼します。実は〇〇が逝去しました・・・・。」ではなく「訃報:〇〇逝去のお知らせと葬儀のご案内」といった風に、訃報であるということが一目でわかるような件名を付けておくようにしましょう。
本文を書く時の注意点
メールの書き方は、基本的には通常の訃報(葉書など)と同じ形式で問題ありません。お葬式の日程などが決まっている場合は、日程も含めて記載するようにしてください。
また、使ってはいけない言葉などにも注意が必要です。
具体的には次の4点に注意をしましょう。
- 忌み言葉を避ける
- 故人様には敬称をもちいる
- 絵文字や機種依存文字は使わない
メールの内容は通常の訃報と基本は同じ
メール本文の内容は、件名と同じように出来るだけわかりやすく簡潔な文章にします。普段からビジネスメールを使用している人であれば、そこまで気にする必要はありません。
記載する内容はお通夜・お葬式の日程が決まっているか(または参列を希望するかどうか)によって異なります。
もし家族葬など、お葬式への参列を希望されない場合や、すでにお葬式が終わっている場合では、下記の項目から日程の部分を省いてください。
- 亡くなった方の名前と日にち(享年)
- お通夜・お葬式の詳細
- 喪主の名前・連絡先
そのほか、ご自身の会社関係の方に送る場合など、忌引期間を書く場合もあります。
【送る相手別】メールの例文紹介
実際にメールを作成するときの、例文を一部ご紹介します。コピーして使用していただけるものですが、適切ご自身の環境に合わせて変更するようにしてください。
親族や友人知人に送る場合の例文【喪主から親族・友人・知人に】
件名:【訃報】〇〇〇〇死去のお知らせ
突然のご連絡失礼いたします。
〇〇〇〇の長男〇〇と申します。
父〇〇が〇〇月〇〇日〇時〇分 享年〇〇歳にて死去いたしました。(病気で入院期間が長い場合などは死因についても軽く触れることもある)
皆様方には生前懇意にしていただき、本当にありがとうございました。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んで通知申し上げます。
通夜ならびに葬儀告別式は下記の通り執り行います。
故 〇〇〇〇 儀 葬儀告別式
通夜 〇〇月〇〇日〇時〇分〜
葬儀告別式 〇〇月〇〇日〇時〇分〜
仏式 真言宗
場所 〇〇斎場(住所: 電話番号: )
喪主 〇〇〇〇(長男)
喪主連絡先 電話番号
勤務先(上司)に送る場合【喪主から上司に】
件名:【訃報】父〇〇〇〇逝去のお知らせ
[役職名] 〇〇 〇〇様実父が死去いたしました。下記ご報告申し上げます。(病気で入院期間が長い場合などは死因についても軽く触れることもある)
死亡者氏名: 〇〇〇〇(享年〇〇歳)
死亡日: 〇〇月〇〇日
忌引連絡: 〇〇月〇〇日〜〇〇日までの〇〇日間、忌引休暇を申請いたします。
忌引中連絡先:電話番号
尚、葬儀は近親者のみの家族葬で執り行う予定です。
また故人の遺志により、一般参列、御香典、弔電、御供物などに関しましては失礼ながら辞退させていただきます。
恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。
[自分の名前]社内で一斉に送る場合【社内の代表(喪主の上司等)から社内に】
件名:【訃報】総務部〇〇〇〇(名前)の御尊父〇〇〇〇様逝去のお知らせ
各位
総務部〇〇〇〇(名前)の御尊父〇〇〇〇殿が、令和〇〇年〇〇月〇〇に享年〇〇歳で逝去しました。
ご冥福をお祈りするとともに、謹んでお知らせ申し上げます。通夜、葬儀告別式は下記のとおり、仏式にて執り行われます。
故 〇〇〇〇 儀 葬儀告別式
通夜 〇〇月〇〇日〇時〇分〜
葬儀告別式 〇〇月〇〇日〇時〇分〜
仏式 真言宗
場所 〇〇斎場(住所: 電話番号: )
喪主 〇〇〇〇(長男)
[メールの差出人の名前・連絡先]社外(取引先等)に送る場合【故人様の部下から取引先に】
件名:【訃報】社長〇〇〇〇逝去のお知らせ
〇〇株式会社 御中
弊社代表取締役社長〇〇〇〇が、令和〇〇年〇〇月〇〇に享年〇〇歳で死去いたしました。
ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んで通知申し上げます。通夜、葬儀告別式は下記のとおり、仏式にて執り行われます。
故 〇〇〇〇 儀 葬儀告別式
通夜 〇〇月〇〇日〇時〇分〜
葬儀告別式 〇〇月〇〇日〇時〇分〜
仏式 真言宗
場所 〇〇斎場(住所: 電話番号: )
喪主 〇〇〇〇(長男)
[メールの差出人の名前・連絡先]なお ご家族の意向によりご厚志については固くご辞退申し上げます。
メールでの訃報は「早く」「小回り」がきく
メールで訃報を出すメリットには、いち早く出せること、小回りがきく(あとで要件を足すことができる)という点が挙げられます。
そのため、故人様が亡くなられたから、まずは訃報の知らせだけを送り、お通夜やお葬式の日程が決まったあとで改めて案内を送る。ということもできます。
メールで訃報を送るタイミング
訃報のタイミングは①故人様が亡くなられた直後②お通夜・お葬式の日程が決まった直後のどちらかに送るのが一般的です。
お葬式や四十九日が終わってひと段落してから訃報メールを出すこともありますが、この場合は時間も取れる状況になっているはずですので、できるだけ正式なもの(はがきなど)で訃報をお伝えするようにしましょう。
メールでの訃報はあくまでも簡易的なもので「すぐに」知らせたときに有効な方法です。
メールで訃報を送るときの順番
訃報を送る順番については、電話でもメールでも変わらず、基本的には故人様の親族や近親者に優先的にお知らせします。もし喪主の立場になる場合は、お葬式の手配が必要になるので、葬儀社関係、菩提寺等へも優先的に訃報を出してください。
その後、友人・知人、会社関係者、町内会などの順番になります。
- 故人様の親族・近親者
- 葬儀社・菩提寺(お葬式の手配関係)
- 友人・知人
- 会社関係(故人様、喪主様)
- 町内会・自治会・ご近所
メールで訃報を受け取った場合はどうしたらいい?
メールやLINEで訃報を受け取った場合、すぐに電話で折り返しをしたくなるところですが、お葬式の手配や精神的な疲労で電話をする余裕がない場合もあります。
関係性にもよりますが、普段から関わりの深い場合を除いては、電話以外の方法で訃報が届いたということを考慮して、同じようにメールやLINEでお悔やみを送るようにしましょう。
お悔やみメールを送る時には次の点に注意してください。
- 言葉遣い(仲がいい人でも敬語を使う)
- 故人様の敬称を使う(父→御尊父様)
- 忌み言葉を避ける
- 句読点は使わない
- 絵文字や機種依存文字は使わない
返信例
件名:〇〇です。心よりお悔やみ申し上げます
この度は御尊父〇〇様の逝去につきまして 心よりお悔やみ申し上げます
先日お話をさせていただいたばかりで 突然の訃報にとても驚いております
何かと大変なときとは存じますが どうぞご無理なさらずお身体ご自愛ください
安らかなご永眠をお祈りいたします
メールで訃報を送るときのよくあるご質問
- メール以外のLINEやチャットでもいいですか?
- 最近ではメールを使わない人も増えてきていますので、関係性によっては普段連絡を取っている手段でお伝えして問題ありません。
- メールの文章の書き方がわかりません。どうしたらいいですか?
- お通夜やお葬式の手配が進んでいるのであれば、担当の葬儀社に文章を作成してもらうことも可能です。また、最低限のマナー(忌み言葉など)を守っていれば、日頃のビジネスメールと同じような書き方でも特に大きな問題はございません。
- メールなら電話と違って夜中でも送っていいですか?
- メールでも通知が届く設定にしている方も多いので、夜間に送ることはあまりおすすめできません。翌日の午前中に送るなど配慮をするようにしましょう。
まとめ
今回の記事ではメールでの訃報の送り方について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
時代の変化とともに訃報の出し方も変わり、最近ではTwitterなどのSNSで訃報が掲載されていることも目にします。
故人様の活動の場所によっても、適した訃報の出し方が変わってくることもありますので、今までの文化や風習を大切にしつつも、時代の変化に合わせた対応を心がけていきたいですね。